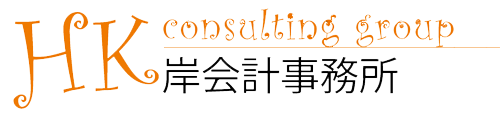遺留分の算定(民法と相続税法の視点から)

相続に関する法務の決め事は民法に定められています。一方で、相続税に関する決め事は相続税法に定められています。相続税法の多くの考え、用語は民法を参考にしています。しかし、民法と相続税法の考え方が異なる論点もいくつかあります。
今回は、遺留分の算定に焦点をあてて、民法と相続税法の違いなどを解説して行きたいと思います。(遺留分侵害額請求については、また別記事にて解説いたします。)
民法の考え方
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人(=遺留分権利者)に最低限保障されている遺産の取得割合をいいます。本来、被相続人が遺言などで自身の財産をどうやって残そうと、被相続人の自由です。これを遺言自由の原則といったりします。
しかし、被相続人が特定の相続人に財産を全て渡すような遺言を書いた場合、他の相続人が不利益を被る可能性があります。したがって、日本の民法は残された相続人の生活保障などの観点から、被相続人の遺言自由の原則に対して、遺留分という制度を作って一定の歯止めをかけています。
遺留分権利者の範囲
遺留分権利者となれるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。つまり、被相続人の配偶者、子、直系尊属が、遺留分権利者になり得ます。また、配偶者は常に遺留分権利者となりますが、子、直系尊属については、相続人の順位の規定に準じます。例えば子がいる場合には、直系尊属は遺留分権利者にはなれません。
遺留分の額、割合
遺留分権利者に保障されている具体的な遺留分の額は以下のように計算します。
遺留分の額=「遺留分の算定の基礎となる財産の価額」×1/2×「遺留分権利者の法定相続分」
※相続人が直系尊属のみの場合には、「1/2」を「1/3」として計算します。
遺留分の算定の基礎となる財産の価額に乗じる、各相続人の遺留分の割合をまとめると以下の通りです。

遺留分の算定の基礎となる財産の価額と生前贈与
遺留分を計算する基礎となる、「遺留分の算定の基礎となる財産の価額」、は以下のように計算します。相続開始時の財産の額に、生前贈与の金額を足して、債務の額を引きます。
「遺留分の算定の基礎となる財産の価額」=「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「被相続人の債務の額」
贈与した財産の価額
「贈与した財産の価額」の範囲に注意が必要です。具体的には以下のようなケースが該当します。
(1)相続人に対する贈与(特別受益)…相続開始前10年以内にされたものに限り、遺留分の算定の基礎に算入する。
(2)相続人以外の者に対する贈与…相続開始前1年以内にされたものに限り、遺留分の算定の基礎に算入する。
(3)贈与者、受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与…(1)、(2)にかかわらず、贈与の時期を問わず全ての贈与を遺留分の算定の基礎に参入する。
特別受益については、遺産分割協議の際の特別受益は贈与の時期を問いませんが、遺留分算定における特別受益は相続開始前10年以内の贈与に限定していることに注意してください。また、贈与財産の価額は、相続開始時の時価で計算する点も注意です
遺留分侵害額請求
遺言などにより取得した財産の額が、上記により求められた遺留分の額を下回る場合には、他の受遺者や相続人に対して遺留分侵害額を請求する意思表示を行うことができます。そして、話し合い、調停、裁判などで問題の解決を図っていきます。遺留分侵害額請求は別記事にてまとめさせていただきます。
特別受益の考え方の違い(遺留分と遺産分割協議)
遺留分算定においては、相続開始前10年以内の特別受益のみが原則として対象となります。一方で、遺産分割協議においては、贈与の時期を問わず全ての特別受益が考慮対象となります。
遺留分算定は、遺言に基づく相続の場合に発生します。遺産分割協議においては、遺留分という概念はありません。
一方で、具体的相続分の算定における特別受益は、遺産分割協議の場合に発生します。
両者の相違を図に表すと以下のとおりです。同じ特別受益という言葉なので分かりづらいのですが、両者は全く異なるケースで使用されている言葉であり、使用されるケースによって、特別受益の対象期間が10年だったり、無期限だったりするわけです。

税務の考え方
遺留分の算定においては、税務上で民法と異なる考え方をすることはありません。具体的に遺留分の侵害額を請求する場合には、税額の計算方法に少し工夫が入ります。
実務家としてのコメント
遺言を書く際に、遺留分の検討は必須です。建前は被相続人が自由に遺言を書けることにはなっていますが、遺留分を侵害するような遺言を書いてしまうと、相続人間の争いの元になります。自分自身の相続人を洗い出し、各相続人がどの程度の遺留分を有しているか試算してから遺言の検討を行うのが良いでしょう。